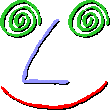 |
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』 ノート |
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』ノート
【まえおき】 【1章】 【2章】 【3章】 【4章】(このページ) 【5章】 【6・7章、付録】
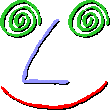 |
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』 ノート |
第4章 近代人における自由の二面性
・プロテスタンティズムの教義……近代的産業組織のもとで果たすべき
役割に対する心理的準備を与えた
‖
パースナリティ全体の形成
−近代的産業組織
個人の発展と同時に無力化 ┐
│をもたらした。
自由の増大と同時に新しい依存┘
・自由の発達過程の弁証法的性格
近代社会機構
↓
2つの仕方で人間に影響
 ̄ ̄‖ ̄ ̄
2つの矛盾する傾向
1)人間はより独立的、自律的、批判的になった
2)人間はより孤立、孤独、恐怖にみちたものになった
・外面的自由と内面的自由
伝統的な束縛(古い権威や束縛)の除去により、
┌→ 人間はよりいっそう多くの自由を獲得したと感じた。
│
│ 一方、
└→ 異なった性質をもつ新しい敵が台頭してきた。
 ̄ ̄ ̄ ̄
新しい敵 = 本質的には外的な束縛ではなく、
パースナリティの自由を十分に実現することを妨げる
内面的な要素
外的権威からの解放により、
┌→ 自由に行動できるようになった。
│
│ と同時に
└→ 匿名の権威(世論や「常識」など)の果たす役割が増大した。
われわれは、外にある力からますます自由になることに有頂天になり、
内にある束縛や恐怖の事実に目をふさいでいる。
・自由の問題はたんに量的なものではなく、質的なものである
・資本主義社会
┌→ 人間を伝統的束縛から解放、
│
│ 積極的な自由を増大、
│
│ 能動的批判的な責任ある自我の成長に貢献
│
└→ 個人 ⇒ ますます孤独で孤立したものとし、
無意味と無力の感情を与えた。
┌ 個人主義的活動の原理 → 個性化の過程を促進
│
│
└ 個人間の紐帯の断ち切り → 個人の孤独化、孤立化
‖
自己否定、禁欲主義
↓
プロテスタントの精神
◇ 個人が経済的目的に手段として服従することは、
資本の蓄積を経済的活動の目的とする
資本主義的生産様式の特殊性にもとづく。
・資本主義の古典的な代表者たち
……働くことを楽しみ、消費することを楽しんだのではなかった。
‖
資本の蓄積のために働くという原理
(もちろん奢侈や「すばらしい浪費」のために
金をばらまく資本家は常に存在した。)
・資本主義的生産様式
┌→ 人間を超人間的な経済的目的のための道具とした
│
└→ プロテスタンティズムによってすでに心理的に準備されていた、
禁欲主義と個人の無意味の精神を増大させた
・プロテスタンティズムの精神と近代的な利己主義の信条との和解
利己心という心理的に複雑な問題を考える必要あり
・近代の利己主義
ルター、カルヴァン┐
│の思想の根底にある仮定 = 利己心と自愛は
カント、フロイト ┘ 同じものである。
~~~~~~~~
↑
フロムによれば、この考えは間違っている。──┘
‖
愛の性質について理論的に誤った考え
⇒ 利己主義と自愛は同一のものでなく、まさに逆のもの。
利己主義とは貪欲の一つ。
利己的な人間……自愛の根本的欠如、深い自己嫌悪。
・近代人の行動
近代人が行動するとき、その関心のもととなっている「自我」
‖
社会的な自我
~~~~~~
社会的な自我とは
……本質的には、
個人に対して外から予想される役割によって構成されている。
……実際には、
社会におかれた人間の客観的な社会的機能を、
たんに主観的に偽装したものにすぎない。
すなわち、
近代的利己主義……真の自我の欲求不満にもとづいた貪欲。
その対象は社会的自我。
・資本主義が個人にもたらした新しい自由
⇔ プロテスタンティズムの宗教的自由が既に与えていた影響を
さらに発展させたもの
・資本主義の独占的傾向の増大
┌ 個人的自我を弱める要素 → 強くなった
│
└ 個人的自我を強める要素 → 弱くなった
このようにして、
┌ 個人の無力感、孤独感の増大、
│ 伝統的束縛からの「自由」がいっそう強く叫ばれる
┌┤
│└ 個人の経済的成果に対する可能性は狭められている
│
└→ 15・16世紀の状況と類似
・独占資本の力が増大
経済組織の一部に資本が集中(富の集中ではない)
│
└→ 個人の創意や勇気や知識に対して成功の機会を封じる。
独占資本が勝利を得た部門
│
└→ 多くの人間の経済的独立が破壊された。
例: 1923年のドイツのインフレーション
1929年のアメリカの恐慌
│
└⇒ 不安の感情を増大。
自分の努力で前進していく希望や、
成功の無限の可能性を信ずる伝統的な信念を粉砕。
各階層への影響
− 小規模なあるいは中程度の実業家
独占的な競争者と戦うこととなった。
頭上にかかる脅威のために、不安と無力さがはるかに増大。
− ホワイトカラー労働者
(およびそのような人間によって成立した新しい中産階級)
巨大な経済的機械の一部で、高度に特殊化した仕事に携わる。
同じような地位にいる他の何百という人々と激しく競争し、
もし落伍すれば、容赦なく追い出される。
− 労働者
何千人という労働者を雇う工場では、
人間はまったく異なる状況におかれる。
「経営」はかれが間接的にしか携わりえない匿名の力であり、
それに対して、かれは個人としてはほとんど無意味。
大企業のなかでは、労働者は、自分の特殊な仕事に関係した
小さな部分しか見渡すことができない。
⇔ 労働組合によるある程度のバランス
↓
しかし不幸にも、
多くの組合はそれ自身巨大な組織に発展し、
個々の成員の創意をいれるような余地はほとんどなくなった。
・現代における個人の無意味さ
┌ 商人や雇人や筋肉労働者の役割
│
│ ばかりでなく、
│
└ 買手としての役割
についてもいえる。
− 買手としての客は、抽象的な買手として意味があるのであって、
具体的な買手としてはまったく意味をもっていない。
− 買手に対する広告の影響
・広告や政治宣伝の方法
┌ 広告……批判的な思考能力を鈍化させる広告方法
│
│ − 理性にではなく感情に訴える。
│
│ − 催眠術の暗示のように、
│ その目的物をまず感情的に印象づけ、
┌┤ それから知的に説明する。
││
││ − あらゆる手段で買手に印象づけようとする。
││
││ − これらすべての方法は、本質的に非合理的。
││
│└ 政治宣伝……個々の選挙人の無意味感を助長
│
│ − スローガンのくりかえし。
│
│ − 問題となっていることと何の関係もないことを強調
│
│ → 選挙人の批判力を麻痺させる。
│
└─→ あからさまに個人の無意味さを強調しているのではない。
その逆に、
個人にへつらい、
かれをいかに重要な存在であるかのようにみたて、
かれの批判的判断や洞察力に訴えるかのようによそおう。
‖
本質的には、
個人の批判力を鈍らせ、
判断の個性的性格を馬鹿にするやり口
・失業や戦争の脅威
・一般の普通人は個人の孤独と無力の感情をまったく意識していない
すなわち、あまりに恐ろしすぎるので意識していない
・二つの道
┌─ 消極的自由から積極的自由へと進む
│
│ ⇒ それができない限り、
│ 自由から逃れようとする
│ ‖
└─ 自由からの逃走
■ 逃避の二つの方法(現代における逃避の主要な社会的通路)
┌ 指導者への隷属……たとえばファシスト国家で起こった
│
└ 強制的画一化 ……民主主義国家に広く行き渡っている
・ファシズムや近代デモクラシーにおける
人間の自動機械化の心理的意味の把握
− 心理的現象をたんに一般的な方法において理解するばかりでなく、
− その機能を詳細に具体的に理解することが必要。
(堀場康一 記)
|