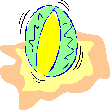 |
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』 ノート |
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』ノート
【まえおき】 【1章】 【2章】 【3章】(このページ) 【4章】 【5章】 【6・7章、付録】
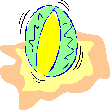 |
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』 ノート |
第3章 宗教改革時代の自由 |
1.中世的背景とルネッサンス ・中世社会の特徴(近代社会との比較) ┌─ 個人的自由の欠如 │ ├─ 近代的意味での個人主義は存在しない、しかし、 │ 実際生活における具体的な個人主義は大いに存在 │ ├─ 第一次的絆による結びつき │ └→ 人間は一般的なカテゴリー(社会的役割)を通してのみ自己を意識 ・中世末期……社会機構、人間のパースナリティの変化 │ | それぞれの階級にとって違った意味 │ └→近代的な意味の個人が出現 ‖ ルネッサンスのイタリア人 −上層階級(富裕な貴族とブルジョア)の文化 −新しい自由 ┌力の増大した感情 │ └孤独と疑惑と懐疑主義、その結果として 不安の感情の増大 ・近代資本主義の経済的機構と精神 中世末期のイタリア文化=ルネッサンスにでなく、 → ┌中部および西部ヨーロッパの経済的社会的状況 │ └ルターやカルヴァンの教義 のうちに見出される。 ・ルネッサンスと宗教改革の比較 ルネッサンス……富裕な強力な少数者が支配 宗教改革 ……都市の中産階級、下層階級、農民の宗教  ̄ ̄ ̄↑ ̄ ̄ ̄ └西欧における近代資本主義の発達の主軸 ⇒ ルネッサンスと宗教改革の精神は異なる ・中世社会の経済的側面 −都市の経済的組織=職人や商人の地位が比較的安定 職人……ギルドが相互の協同にもとづき、その成員に対して 比較的安定性を与えた 商業……多くの小規模な商人により行われた −経済生活に関する根本的な二つの仮定 1)経済的利益は生活の真実の営み(それは救いにほかならない) に従属している 2)経済的活動は人間的行為の一面であって、人間的行為の他の面 と同じく、道徳律に結びつけられている ・経済的変化のいちじるしい結果 中世末期……職人や商人の比較的安定した地位がくつがえされ、 16世紀には完全に崩壊 中世的社会組織の崩壊……中世的社会組織が与えていた、固定性と 比較的な安定性も破壊 ◇ 資本主義の発達に伴い社会のすべての階級が動き始めた → 市場の新しい機能、競争の役割の増大 → 資本主義による個人の解放 人間は自己の運命の主人となり、危険も勝利もすべて自己の ものとなった。 ・自由の多義性 もたらされた新しい自由……動揺、無力、懐疑、孤独、不安 の感情を生み出す | ↓ ◇ このようなときに、ルター主義とカルヴィニズムが出現 |
2.宗教改革の時代 ・宗教的教義や政治的原理の心理的意味の分析における留意点 ┌心理学的分析……その原理の真理性についての判断は含まない │ └二つの問題の区別……指導者の心理的動機と支持者の心理的動機 ・思想分析の課題 1)ある思想がイデオロギーの全体系の中に占める重さの決定 2)思想の真の意味とは違う、合理化の面の取扱いの決定 ・カトリック教会の精神と宗教改革の精神との本質的なちがい ・ルター −ルターの体系 カトリック的伝統と異なるという意味で二つの面をもつ (1)プロテスタント国家でルターの教義が解釈される場合、 ルターが宗教的問題で人間に独立性を与えたことを指摘する (2)人間の根本的な悪と無力の強調(ルターおよびカルヴァン) ←→近代的自由のもう一つの面である、 個人にもたらされた孤独と無力 −ルターの思想の根本概念……人間の本性は自然的不可避的に悪であり 背徳的である ┐ 自分の努力ではどのような善も│ なしえない、人間の腐敗と無力│─→ 神の恩寵の成立する とを確信すること │ 本質的な条件 ┘ −非合理的な懐疑(←→孤独と無力との関係) │ └外界に対し不安と嫌悪の態度をとる人間の孤独と無力から生じた 非合理的な懐疑は合理的解答によって解決できない │ ↓ 確実性への強烈な追求  ̄ ̄ ̄ ̄│ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ └─純粋な信仰の表現ではなく、 耐えられない懐疑を克服しようとする要求に根ざす ・中産階級の位置……非常に富裕な階級と非常に貧しい階級との中間 │ ↓ 中産階級のディレンマの反映 = ルターの人間像 −「権威主義的性格」の典型的な特徴 ┌権威を愛する気持ち ┐ → 同時に存在 └無力な人間に対する憎悪の気持ち┘ ・カルヴァン −思想全体の中心テーマ=自我の否定と人間的プライドの破壊 │ ↓ 完全な服従と徹底的な自我の否定によって、 個人は新しい安定を期待できる −ルターとの違い ┌ カルヴァンの予定説 │ (アウグスティヌス、アクィナス、ルターの予定説と異なる) │ │ ・神はあるものに恩寵を予定するばかりでなく、 │ 他のものには永劫の罰を決定すると、カルヴァンは説く │ │ 人間の根本的な不平等という原理 ⇒ ナチのイデオロギーに復活 │ └ カルヴァンは道徳的努力と道徳生活の重要性をいっそう強調 個人が自らの行為でその運命を変えることができるのではない。 ─→努力することができることそれ自体が、救われた人間に 属する一つの証拠である。 ‖ たえまない人間の努力の必要性 ┌ 個人は疑いと無力さの感情を克服するために、 │ 活動しなければならない。 │ └ 内的な強制により仕事に駆り立てられる、強迫的性質 ・新しい宗教的原理(プロテスタンティズム)の意味 中産階級一般の人々が感じていたことを表現しただけではない。 ↓ その態度を合理化し体系化することにより、ますます拡大強化した。 ↓ さらに個人に不安と取り組む道を教えた。すなわち、 −自己の無力さと人間性の罪悪性を徹底的に承認。 −極度の自己卑下とたえまない努力によって、その疑いと不安を 克服することができると教えた。 ・新しい性格構造 ◎資本主義社会の生産的な力となった性格特性 ‖ 人間のエネルギーが特殊な形に形成されたもの −仕事への衝動 −節約しようとする情熱 −たやすく超個人的な目的のための道具となろうとする傾向 −禁欲主義 −義務の強制的意識 ・新しく形成された性格特性に応じた行動 ─→経済的必要という見地から、実際に利益があった。 ─→新しいパースナリティの欲求と不安とに応えるものだった。 したがって、心理的な満足を与えた。 ⇒ この原則をもっと一般的な言葉でいうと、 「社会過程は、個人の生活様式を決定することによって、 すなわち他人や仕事に対する関係を決定することによって、 個人の性格構造を形成する。」 新しいイデオロギー……この変化した性格構造から結果し、また、 それに訴える。 (堀場康一 記) |